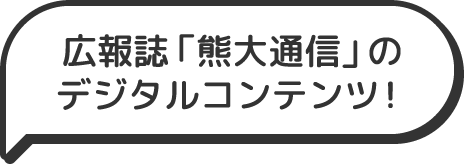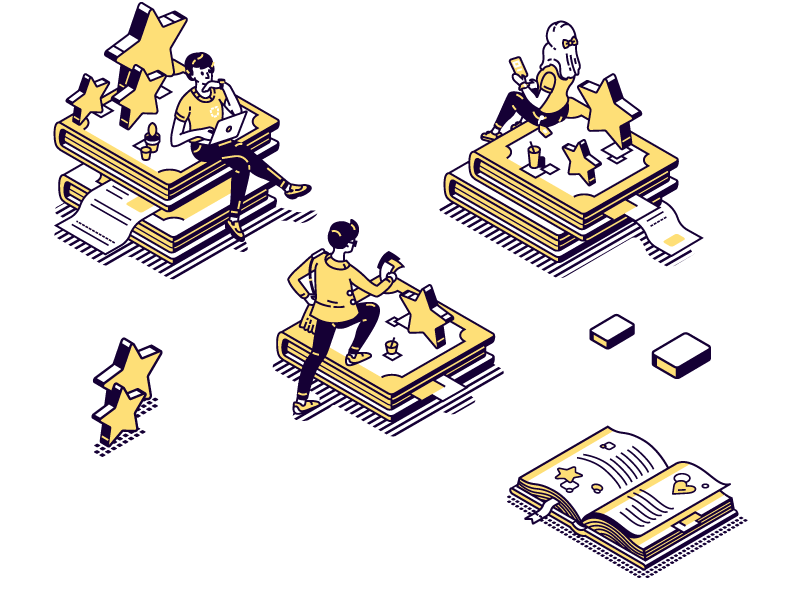- ホーム
- 熊大通信
- Vol .93(2025年 SUMMER)
- 研究室探訪 熊本大学整形外科学講座
整形外科疾患の病態解明や治療法開発、予防法の確立も視野に研究にまい進
熊本大学整形外科学講座では、大きく分けて、整形外科疾患のメカニズム解明などの基礎研究と、同じ疾患を持つ患者さんを追跡・観察する分析疫学の手法の一つであるコホート研究という臨床研究、この2つに取り組んでいます。
基礎研究で扱っている一例が骨粗しょう症。疾患のメカニズムを明らかにするため、マウスの細胞を培養し骨を吸収する破骨細胞と呼ばれる細胞をつくったり、遺伝子を見るなどの研究を進めています。治療標的や薬剤も探索し、近い将来に臨床応用ができることも目標の一つです。
コホート研究として進めている一つが大腿骨の骨折。骨折した患者さんの様々な情報を集めて分析。そうすると、折れるリスクになる要因を把握でき、骨折予防につなげることが可能です。データは、熊本県の病院や施設はもちろん、県や市町村という自治体とも連携し収集。自治体と協働でこのような研究を進める大学の研究室は珍しい存在です。
整形外科学講座を率いる宮本健史教授に聞きました!
研究者の成長を、地域や患者さんの利益につなげたい
熊本大学の整形外科学講座には、リハビリテーションや、骨粗しょう症と共通の疾患がある歯科口腔外科からの大学院生もいます。私は慶應義塾大学医学部の整形外科学も兼任しているため、合わせると研究メンバーは私を含め37人です。
人生の中の貴重な時間を使って研究する以上、私は、研究がその人の成長につながってほしいと思っています。個人の成長が組織の成長につながり、さらに彼らが学会等に参加して常に新しい情報に触れ、それを熊本にもたらしてくれれば、地域医療にもプラスになります。個人の成長が組織の成長に、そしてそれが地域と患者さんの利益にもつながっていく、そんな良い流れを構築することが、自分の仕事だと考えています。

- 大学院生命科学研究部 総合医薬科学部門
感覚・運動医学分野 整形外科学講座 - 宮本 健史 教授

-
根治させる治療薬がない骨腫瘍を研究
- 博士課程4年
- 島田 真樹 医師

研修医として2年間、整形外科に入局して臨床医として5年間経験を積んだあと、この整形外科学講座に入りました。宮本教授は骨粗しょう症研究では著名な先生。この講座では宮本教授のもと、全員が、それぞれの目標や熱意をもって日々研究にいそしんでいます。
私は、根治させる薬がまだない疾患である骨腫瘍のうちの一つを研究しています。腫瘍に特徴的な遺伝子の変化はわかっているのですが、その変化が何を意味するかなどはわかっていません。それを明らかにして、薬など治療方法の開発につながれば、と考えています。
今年が博士課程最後の1年。修了後は整形外科の執刀医として実臨床に携わりたいと考えています。外科系分野は手術に必要な手技を磨く必要があり、研究だけに没頭する時間をもったいないと感じる人もいるかもしれません。しかし、ものの考え方や見方を突き詰められる研究を行う4年間は、決してブランクにはなりません。臨床医として誰もが持つ疑問や課題を、一度基本に立ち返って研究という形で探究できるのは魅力だと思います。
-
大腿骨骨折のデータを収集分析するコホート研究
- 博士課程4年
- 髙田 柊 医師

熊本県内にある総合病院の常勤医として勤務しつつ、週に1度、熊本大学の整形外科学講座で研究を進めています。行っているのは、大腿骨の付け根部分の骨折である大腿骨近位部骨折に関するコホート研究。骨粗しょう症は骨折を繰り返す特徴があります。両側にある大腿骨の片方を骨折し、さらにもう片方が折れる因子になるものは何か。最初の骨折のデータをもとに、その後もう片方も骨折したか否か、要介護度はどうなったか、亡くなってしまったか、その3つに関して1年後のデータを収集。時間をかけて観察し分析することで予防法の確立を目指す研究です。
博士課程修了後は整形外科医として、手術はもちろん、手術をしない保存的治療など、患者さんに適した医療が提供できることが理想です。もちろん、研究に費やす時間もとても有意義だと思います。エビデンスや医療指針に基づいて医療を行うのが医師。そのエビデンスがどんな研究から得られているのか、指針がどう作られているのかを、臨床研究を通して学ぶことができています。
- メンバー構成
- 教授1名、講師1名、助教8名(特任助教含む)、医員5名、社会人大学院生14名、大学院生8名(整形外科・リハビリテーション科・慶應義塾大学を含む)
- 学位テーマ
-
- 大腿骨近位部骨折発症と関連する因子の同定
- サイトカインIL-17による骨肉腫発症機構の解明
- 黄色靭帯および硬膜下脂肪腫アミロイドーシスによる腰部脊柱管狭窄症発症機構の解明
- 軟骨組織に発現するEnpp1による異所性石灰化・骨化と老化制御
- 肩腱板修復におけるScx/Sox9二重陽性細胞の動員とその役割
- 前十字靭帯再建術後の靱帯修復におけるScx/Sox9二重陽性細胞の動員と遺残靱帯の役割
- 肩腱板修復におけるScx/Sox9二重陽性細胞の動員と加齢による変化
- 骨折治癒促進性マグネシウム合金プレートの開発
- TNFα-mTOR軸による異所性骨化超高齢者における骨粗鬆症とサルコペニアの有意な相関と両疾患におけるIGF1低下の意義
記事を探す
- キーワード検索
-
- 検索対象
-
- 所属別
-
- 検索対象
-

 翻訳
翻訳