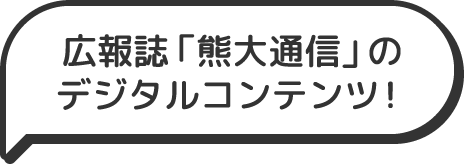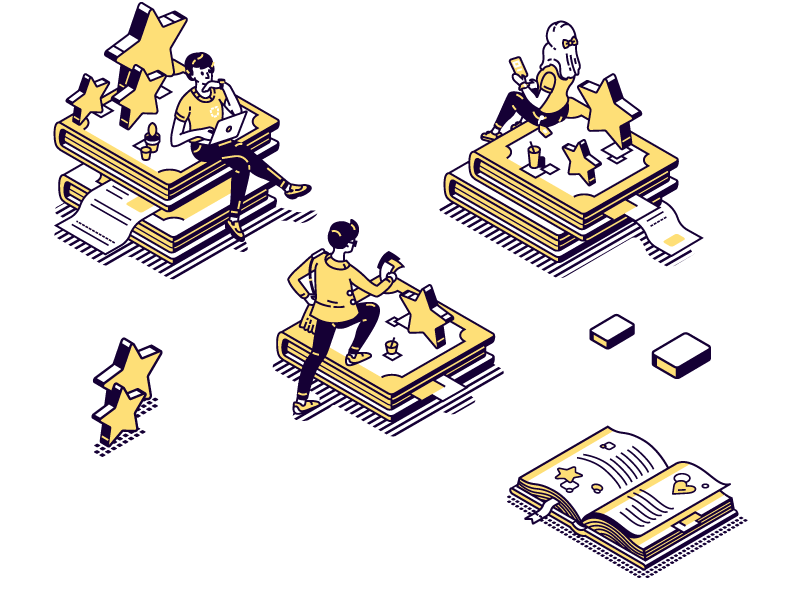- ホーム
- 熊大通信
- Vol.90(2023年10月)
- 進化し続けてまだ見ぬ世界を探求する 発生医学
発生研 生命の本質を探る
熊本大学発生医学研究所(以下、発生研)は、日本でたった一つの「発生医学」の研究所です。
「発生医学」とは、本研究所が設立された歴史の中で、ここ熊本大学で生まれた言葉です。
発生研では、さまざまな分野の研究者が集い、日々、生命の謎の解明に挑んでいます。
今回の特集では、発生研で生命の謎に挑む研究者たちに基礎研究の魅力とのその思いについて聞きました。
INTERVIEW 進化し続けてまだ見ぬ世界を探求する発生医学
 |
|
発生医学研究所長 幹細胞部門 多能性幹細胞分野 |
| 「肥後医育ミュージアム」を訪れた丹羽教授。 館内には熊本大学医学部の全卒業生の氏名が記されている圧巻のコーナーも |
“医学の目”で“発生学”を研究
発生とは一個の卵が個体になる全過程を指し、その過程を明らかにすることが、医学の発展に結びつくと考えています。つまり「医学」と、基礎研究としての「発生学」を橋渡しするのが発生研の特徴です。しかし、全ての研究が医学的応用を目指しているかといえば、そうではありません。“医学の目”を持ちながら発生学を研究し、そこに可能性を見出せば、応用につなげていく。あくまでも発生学ありきでやることで、それまで見えてこなかった医学とのつながりが見え、やがて人類に寄与する成果をもたらすと私は考えています。
生命の設計図を解き明かしたい
生き物は「卵が固体になる過程」をたどりますが、その過程は分からないことだらけです。哺乳動物の受精卵を比較すると、卵を見ただけではヒトなのか、他の動物なのか、見分けがつかないほど似ています。しかし、受精卵の中の遺伝子構造によって、間違いなくヒトになる。そして「それはなぜか?」という問いに、いまだ誰も答えられないのです。
マウスの受精卵の遺伝情報はCD-ROM1枚程度に収まるほどの情報量しかありません。それが全ての生物を形作る命の設計図なのに、それがなぜマウスやゾウ、ヒトになるのか、人類はいまだ解き明かすことができていない。我々は太古から伝わった1枚のディスクを前に、それを読み出す機械を持っていないのです。そこをなんとか解き明かしたいという思いで研究に取り組んでいます。
研究とは、自問自答の繰り返し
私はいろいろな臓器になることができる多能性幹細胞の謎を解き明かそうと、マウスのES細胞を使って多能性を維持する分子機構の解明に取り組んでいます。
研究は、自問自答の繰り返し。研究者は、自分が疑問に思ったことが、科学的な問いになっているかどうかを見極め、誰もが認めるようなアプローチで解き明かしていくことが大切です。しかし“十中七、八”はうまくいきません。仮説が間違っていたのか、技術や方法論が問題なのかを検証していくと、次の研究へのヒントが見えてくる瞬間があります。「どこまで面白いと思えるか?」「失敗も面白いと思えるか?」が成功のカギともいえるのではないでしょうか。
誰も見たことがない世界へ
発生研では、多様な分野の研究者による分野融合を進めています。マイクロデバイスを研究に使用することも多く、データサイエンスの領域でスキルを持つ人材など、多彩な専門家に門戸を開くことで、さらに探究できるエリアが広がると考えています。
基礎研究の魅力は、誰も見たことがないものを自分で探し、いまだない答えを自分が見つけること。発生研では、さまざまな研究者がアカデミックに論理的に、誰も見たことがない世界を探究しています。研究がうまくいった時の快感は一言では言い表せません。だから基礎研究はやめられないんです。
記事を探す
- キーワード検索
-
- 検索対象
-
- 所属別
-
- 検索対象
-

 翻訳
翻訳