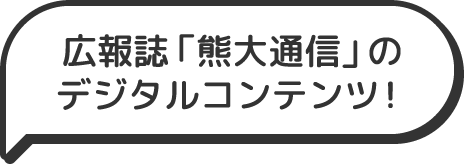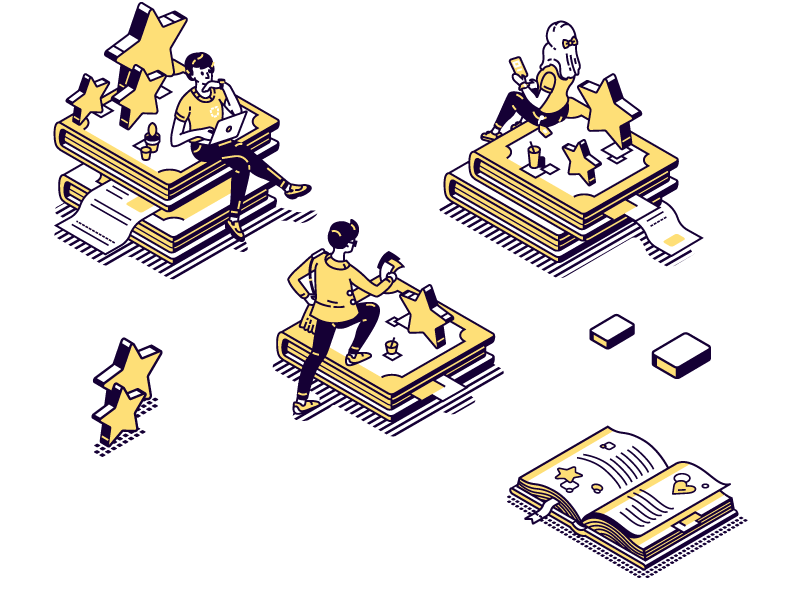- ホーム
- 熊大通信
- Vol .92(2024年4月)
- 研究室探訪 -熊本大学大学院先端科学研究部(工学系)柿本・安藤研究室
しなやかな社会基盤を創造し、自然災害に強いまちをつくる
熊本大学大学院先端科学研究部(工学系)柿本・安藤研究室 Civil Engineering Laboratory
安全・安心な生活を支える社会インフラをデザインする学問「土木計画」を探究する柿本・安藤研究室を訪ねました。
|
|
|
| くまもと水循環・減災研究教育センター 柿本 竜治 センター長・教授 |
くまもと水循環・減災研究教育センター 安藤 宏恵 助教 |
| 専門は土木計画学。行政の意思決定に役立つような土地利用から公共交通まで幅広いテーマで研究を行っています。週に1度の合同ゼミでは、安藤助教が異なる視点で物事を捉えて、多様な意見をもらえるので大変助かります。 | 土木計画学の中でも交通工学を専門に、交通に関する多様な技術や交通ネットワーク、災害時の交通などを分析しています。座右の銘は「耐雪梅花麗(雪に耐えて梅花麗し)」。辛いときもいつか花開くときを信じて、また研究に向かう力をくれる言葉です。 |
土木計画学 よりよい社会を構築するために都市や交通をデザインする学問領域
都市圏全体の効率化と安全性を向上 レジリエントな社会の形成を目指して
交通工学を専門とする安藤助教が探究しているテーマの一つが道路ネットワーク。都市圏全体の効率化を図るために、移動時間や燃費、安全性などを指標に多角的な分析を行うほか、地震や洪水などの自然災害に備えて、う回路が少ない場所や孤立が発生しそうな地域を数理モデルで見つける研究を行っています。「災害や危機に負けないレジリエントな社会を創るのが目標です」と安藤助教は語ります。
 |
 |
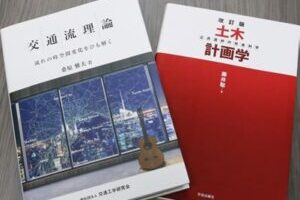 |
| 「熊本都市圏道路網」は、あらゆる研究のデータベースとなる道路ネットワーク。 令和4年度は、自動運転専用レーンを設置するならどの道路にすると都市圏全体の利益となるのかを研究。 |
「令和2年7月豪雨」では、国道・県道や鉄道なども甚大な被害を受け、球磨川に架かる橋梁のうち10橋が流出した。 写真は大きな被害が出た球磨川の橋梁の一つ。災害の影響で社会インフラが破損してしまった一例だ。 |
柿本・安藤研究室では、同研究室の学生だけでなく、他の研究室の学生へも交通理論ゼミを行っている。 「他の学生の視点や意見などを生かして成長してほしい」と安藤助教。写真は交通理論ゼミで使用する教科書。 |
社会基盤の構築からまちづくりまで 暮らしに根付いた魅力ある分野
 |
|
大学院自然科学教育部 |
熊本市内の「自転車の走行しやすさ」を評価する研究を行っています。自転車利用者が感じる「走行しやすさ」が道路属性の違いによってどのように変化するのか調査したり、自転車レーンの整備計画が走行しやすさにどのように影響するかを考察しています。土木はI T(情報技術)などと同様に暮らしに根付いている分野で、社会基盤の構築からまちづくりなども含めて、人が生活していく上で決してなくなることがない領域です。それは大きな魅力ですね。
都市構造の経年変化を分析 建設コンサルタントの道へ
 |
|
工学部土木建築学科4年 |
熊本市が目標とする“多核連携都市”に適切に向かっているかを検証するため、複数の「コンパクトシティ評価指標」を用いて都市構造の経年変化を分析する研究を行っています。都市開発に携わる知見や都市構造の因果関係など、熊本市を一つの事例として学ぶことが目標です。GIS(地理情報システムソフト)を使いこなすのは大変な一方で、活用できた際には自分の成長を感じることができ、やりがいにもつながっています。
Seedsの未来
研究が目指す未来は「災害に強いまちづくり」。これまで道路網を中心に研究してきましたが、災害に強いまちをつくるという観点から、道路だけでなく情報ネットワークやライフラインなどインフラとの関わりを踏まえた研究を目指します。
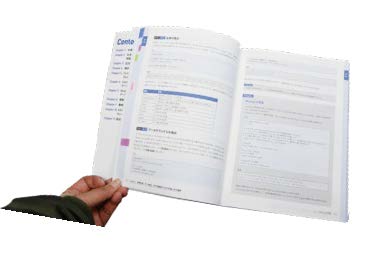
研究室をのぞいてみよう!!
記事を探す
- キーワード検索
-
- 検索対象
-
- 所属別
-
- 検索対象
-

 翻訳
翻訳