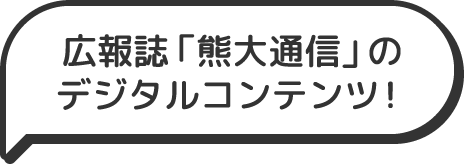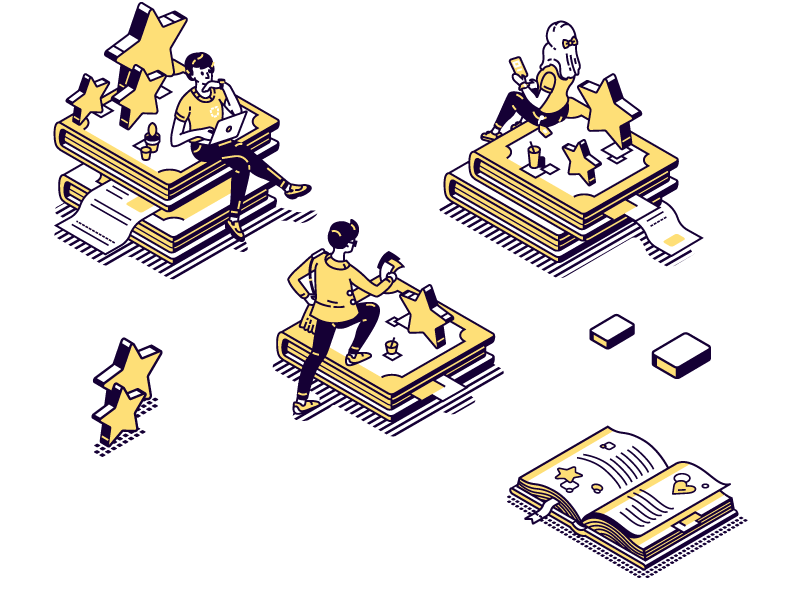- ホーム
- 熊大通信
- Vol.91(2024年1月)
- 熊大発!オンリーワンの 半導体教育で未来を描く
~学生が自ら学び、育つクリエイティブな場へ~
熊本大学は、2024(令和6)年4月に開設される「情報融合学環」(DS半導体コース)と「工学部半導体デバイス工学課程」で、世界をリードする高度半導体人材の育成を目指します。
今回は、重要文化財「工学部研究資料館」(旧機械実験工場)を舞台に、新たな熊大の教育に携わる飯田全広教授と松田元秀教授によるトークセッションをお届けします。
本学の前身の一つ「熊本高等工業学校」(1906(明治39)年設立)時代、生徒たちが機械実験を学んだ場で、新たに始まる半導体教育の特長や教育にかける想いを聞きました。
熊本は半導体人材育成の拠点としておもしろい
 |
|
半導体・デジタル研究教育機構 2016(平成28)年大学院自然科学研究科教授などを経て、2023(令和5)年より現職。 |
首藤(コーディネーター) 新生「シリコンアイランド九州」のカギを担う熊大の新たなフェーズがいよいよスタートします。これまでの先生方のご経験から見えてくる現状をお聞かせください。
松田 私は現在、材料工学分野を専門として教育研究に取り組んでいますが、学時代は電子・通信分野の学科で学び、半導体に大変関心を持っていました。その当時1980年代頃は、まさに半導体ブームであり、日本が半導体市場の世界シェアの多くを占めていました。その後は、皆さんがご存知のとおり日本が競争力を失ったことで、半導体業界の規模縮小が起こり、学生時代の仲間たちが大変な思いをしていることを目の当たりにしました。この影響を受けた現在、日本の半導体人材が空洞化しているのです。今回、工学部半導体デバイス工学課程長に着任し、学生時代に感じていた思いをつなげられればと思っています。
飯田 私は工学部の電子工学科出身で大学院では情報工学を専攻するなど、色々なことをやってきました。半導体人材の空洞化・縮小は、30年ほど続いていましたが、半導体の国内生産が強化される昨今、大学が人材を輩出することが肝要だと考えています。九州には半導体関連企業が集積している「シリコンアイランド九州」という特性もあり、もう一度半導体業界を盛り上げるには、熊本、九州が大きな役割を果たすと考えています。
首藤 半導体人材育成の拠点として、熊本はおもしろくなりそうですか。松田 私はそう確信しています。北海道、東北、広島など半導体産業を盛り上げようという地域が色々とありますが、九州の半導体人材育成拠点として、熊本はおもしろい場所になると思います。
飯田 高度半導体人材の育成は大学で担う重要な役割だと思っています。特に熊本は、他の地域と比較して半導体関連企業が集積していることもあり、熊大が育成する半導体人材への企業のニーズは高く、人材を輩出する意義が高いと考えています。
首藤 人材育成拠点と半導体産業拠点の連携、地の利が熊本にはあるということですね。国内の半導体拠点同士の連携、オールジャパンの動きはこれからですか。
飯田 本学では東京大学、九州大学と連携していますし、熊本県と北海道でも半導体分野で連携強化の協定が結ばれました。産官学どのフェーズでも動きが加速しています。
 |
|
大学院先端科学研究部(工学系)
2008(平成20)年大学院自然科学研究科教授を経て、2016(平成28)年より現職。 |
熊大が半導体教育のオンリーワンに
首藤 「情報融合学環」や日本初の半導体に特化した学士課程「工学部半導体デバイス工学課程」など、新しいキーワードを熊大がつくりました。
飯田 今回のような半導体業界の盛り上がりがある前から、熊大では大学改革の一環として、データサイエンスの強化をはじめとした情報系分野の再編などを進めていました。「半導体人材」には主に2種類あると考えています。一つは、半導体に関わる個々の技術に習熟・精通した人材で、松田先生が課程長である「工学部半導体デバイス工学課程」で育成する人材です。もう一つは、DX(デジタルトランスフォーメーション)、数理、データサイエンスの素養を身に付け、DX課題に対応できる人材であり、複雑な半導体製造工程を最適化できる人材です。これが、私が所属する「情報融合学環」の「DS半導体コース」で育成する人材です。半導体の製造工程には数十万、数百万にものぼるパラメーターがあります。これを人間の経験や手作業で行うことはもはや難しいため、データサイエンスを用いて生産を最適化する人材が必要です。実際、4~5年ほど前に企業側からこの
ような人材輩出の要望があり、議論を重ねてきました。他大学でもさまざまな半導体人材育成の動きがありますが、このような経緯や小川学長のリーダーシップもあり、熊大はいち早くスタートを切ることができたと考えています。
首藤 「情報融合学環」や「工学部半導体デバイス工学課程」の仕組みもユニークだと感じています。
飯田 「情報融合学環」について、他大学にもいわゆる情報系の学部組織はあるものの、先ほどお話した「DS半導体コース」のような半導体関係のコースがあることは非常にユニークで、他にはないと思います。また、この学環は「文理融合」も特徴です。「DS半導体コース」とは別に「DS総合コース」があり、このコースでは、熊大の法学部や東海大学の経済系の科目を履修することが可能です。学環は「DS総合コース」をベースとしており、そこからさらに各学問分野に特化したコースをつくることができるようにしています。「DS半導体コース」がその一つです。今後必要に応じて、例えば「DS医学コース」や「DS薬学コース」のような新たなコースができるかもしれません。
松田 「工学部半導体デバイス工学課程」のユニークなところは、何といっても半導体技術者・研究者の育成に特化した日本初の学士課程であることです。「課程」とは、「学科」と同等の組織ですが、一つの学問分野を集中的に学習する「学科」とは異なり、材料・化学・電気・電子・情報・機械など、半導体に必要な学問領域を、いわば横串を通して、学問分野横断的に学ぶことができます。
首藤 半導体教育における熊大の強みは他にどのようなものがありますか。
松田 飯田先生からも話がありましたが、やはり世界で活躍する企業が熊本をはじめとした、「シリコンアイランド九州」に集まっている、身近にあるという産業的バックボーンは熊大の強みだと思います。今の時代、どこにいてもオンラインで繋がり、話すことはできますが、工学系は、製品を自分の手で触ってみることが大切だと思っています。
飯田 企業が身近にあることで、インターンシップなどを通じて、単に情報を扱うことに精通した人材ではない、製造工程も理解できる人になります。このような企業との連携は、これからさらに熊大でも模索しますし、企業も期待していると思います。
首藤 このユニークな仕組みやバックボーンを生かして、ぜひ熊大を半導体教育のオンリーワンにしたいですね。
熊大が目指す半導体教育
首藤 “教育”は大学の重要な役割です。今後の半導体教育で予定していることや先生方が教育で大切にしていることを教えてください。例えば、受験などと異なり、唯一解=ただ一つの正解がないことを学んでもらうこともその一つだと思いますが。
松田 現在、半導体関連企業と議論を重ねているところですが、半導体関連企業で求められていることについて、実際に企業の方を招いて学生に課題を設定してもらう、いわゆるPBL(課題解決型学習)型の授業などのカリキュラムを予定しています。また、唯一解がないことを学ぶことは確かに重要だと思います。私が研究室の学生にいつも伝えていることは、予想だにしない失敗をしたとき、なぜそれが起きたのか、とにかく考えて、分析・判断し、優先順位をつけて改善を重ねることです。大学に「育ててもらおう」ではなく、「自分で育つんだ」という意識が大切だと思います。学びの場として、この熊大を上手く活用してほしいですね。
飯田 人の話を聞いて分かった気になっているのと実際「できる」のは違います。人は自分で実践して理解・納得したものしか「できる」ようになりません。大学では失敗すること、答えがわからないものにこそ価値があると思います。
松田 「失敗」を認めることは本当に大切です。工学系などの学問分野にかかわらず、自分が考えたことが上手くいった、実現できたときはうれしいのではないでしょうか。
首藤 半導体の人材育成の観点からいうと、半導体の知識・技術やデータサイエンスを武器として、いまだ答えがないことに対して取り組んでいくということですね。
飯田 そうです。先ほど松田先生から話があったPBLのことも「情報融合学環」でいえば、例えば、企業からデータを提供してもらい、データサイエンスを活用して分析し、何らかの答えを出すことが想定されます。このような現場の生のデータを用いて「何がわかるか」を探究することを予定しています。PBLに限らず、座学でも答えのない世界にどう向き合うのか、しっかり学ぶことができるカリキュラムを構築したいと思っています。今回の新たな学部相当組織・課程の開設は、これをさらに推進するチャンスだと考えています。
首藤 ひと口に半導体人材といっても、半導体研究や製造の場で活躍するなど、さまざまな人材像がありますが、熊大が育成を目指す半導体人材像について教えてください。
松田 熊本ならではの、3つの利点「地の利(立地・周辺環境・企業との連携)、知の利(半導体研究・教育環境)、ち値の利(データサイエンス)」を活かし、研究の場であっても、製造の場であっても、課題意識を持ち、リーダシップを発揮できる人材であってほしいと思っています。
飯田 現在、企業から大学に対しては、多くの高度半導体人材を輩出することに期待があると感じています。そのため、大切なことは、熊大で半導体に関する高い専門性を身に付け、一人ひとりの学生が自分なりの考えや思いで将来ビジョンを描くことができるようになることかと思います。熊大で育つ人材が、責任感と自覚を持って、世界の半導体業界を牽引する存在になってほしいです。
首藤 新生「シリコンアイランド九州」の実現に向け、教育・研究に向き合う先生方の熱い想いに感銘を受けました。今後の半導体業界をオールジャパンで盛り上げる旗を振るのは、ここ熊大でありたいですね。ありがとうございました。
Impression
半導体とデータサイエンスに関わる研究・人材育成、そして社会実装の拠点として、熊本大学が大きく羽ばたこうとしていることがよくわかりました。工学系の先生方のお考えに触れ、薬学系教員として、教育・研究に携わる身としては、人材育成や研究にかける思いで共感できる部分がたくさんありました。新たな2つの教育組織の開設が目前に迫る中、新たな年が始まりました。「シン・熊本大学」を象徴する画期的な教育体制がいよいよスタートします。
記事を探す
- キーワード検索
-
- 検索対象
-
- 所属別
-
- 検索対象
-

 翻訳
翻訳