発生研の若手研究者が語る だから基礎研究はやめられない!
- 所属
「肥後医育ミュージアム」(熊本大学本荘キャンパス)には、本学を含めた熊本の医学教育の歴史が展示されています。
本特集では、生命の謎に挑戦し続けている、新進気鋭の5人の研究者たちが同ミュージアムに集い、発生研の歴史や伝統に触れるひとときを企画。基礎研究に魅せられた研究者の日常と研究にかける思いを座談会でお届けいたします。

発生制御部門 染色体制御分野 石黒 啓一郎 教授

器官構築部門 筋発生再生分野小野 悠介 教授

幹細胞部門 組織幹細胞分野古賀 沙緒里 助教

幹細胞部門 胎盤発生分野岡江 寛明 教授

発生制御部門 細胞医学分野日野 信次朗 准教授
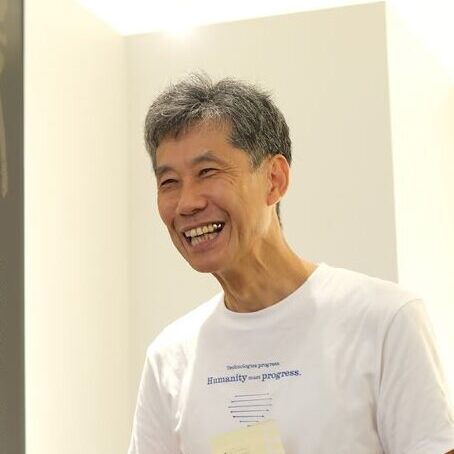
大学院先端科学研究部(理学系)小出 眞路 教授
石黒 初めて「肥後医育ミュージアム」を訪れて、熊本の医学教育の歴史の延長線上に私たちの研究があることを感じ、感慨深いものがありました。発生医学研究(以下、発生研)の歴史も刻まれているこの場所にお集まりいただいた、現在活躍中の若手研究者の皆さん、基礎研究の面白さや研究者となったバックグラウンドなどをお聞かせください。
小野 私は、小・中学校から大学までサッカーをやっていたことがきっかけで、大学で運動生理学などを学び、「筋肉のためにはどのように運動やトレーニングをすればよいか」「壊れた筋肉はどのように再生するのか」などの素朴な疑問をちゃんと基礎から理解したいと、この研究に入りました。
岡江 私は、生き物が好きだったことが、やっぱり大きいかな。ネズミの初期発生を研究していたのですが、解剖している時にふと胎盤が気になり、胎盤の発生や機能に関する今の研究に入ったという感じです。面白いこと、面白いものを多角的なアプローチで解いていくところが、基礎研究の面白さだと思っています。
古賀 私は、小学生の時に「新しい薬を創って、治らない病気をなくしたい」と心に決めて薬学部を目指し、学生時代も「早く研究室に入って研究したい」と思っていました。
石黒 薬剤師になる道もあったと思いますが、なぜ基礎研究を目指したんですか?
古賀 「今ある薬を患者さんに届けることも大切ですが、私は今ない薬を作りたい」という思いが強かったです。実験がとにかく楽しくて、飽きることはありません。毎日が新鮮で、常に新しいものに触れ合えるし、何歳になっても学べる。私にとって研究は、変わることなく楽しいものなんです。
石黒 日野さんは農学部出身ですね、なぜ研究者の道へ?
日野 私も古賀さんと同じく研究自体が好きですね。自分で調べて、自分で考えた仮定を、実際に自らの手で確認するのは、研究者の醍醐味ですから。
石黒 何が日野さんを研究のとりこ虜にさせたんですか?
日野 研究は日常生活だから、何か決定的な出来事があったわけではなくて、研究できる日常が楽しかったし、それが自分になじんだということかなと思います。
石黒 私は、実験をやっても結果が出ないし、こんなので博士になれるのかとか就職できるのかと、不安になった時期がありました。皆さんは思うように研究が進まず、自分を見失いかけた経験はありますか?
小野 もちろん失敗は数え切れないほどあります。それを踏まえて、複数の研究を並行して走らせるなどして、うまくいかなかった時には別の研究で精神的なバランスを取るような工夫は大学院の頃からやってました。
岡江 私も結構、いやもう常に悩んでる感じはありますね。でも、運や周りの人に恵まれて、支えられていると強く感じています。
石黒 皆さん、研究室では、どのような指導体制ですか?研究室ごとにカラーがあるのではないかと興味があります。
古賀 学生時代に所属していた研究室では、4つのグループがあって、博士が修士を、修士が学部生をと、順番に指導する体制でした。
日野 先輩から教えてもらうのは、どこでもありますね。最初研究室に入ると、研究テーマを書いた紙を渡されて、選んだテーマによって、博士をはじめとする縦割りで教えるところもありました。
小野 学生の時は何やっても良いって感じでしたね。何をやりたいかを先生に相談するのですが、調べれば調べるほど、やりたいことがどんどん変わってしまい、先生にあきれられたことがあります。その経験から、私の研究室では、テーマを複数用意して選んでもらうようにしています。もし興味がなかったら違うテーマを考えます。
岡江 個人的な経験からいうともらったテーマって、だいたいうまくいかないんですよね。それで私の研究室では、大まかにテーマを伝えますけど、細かい実験に関しては、本人と相談しながら進めていく。ある程度自由に選択できる環境です。
石黒 「与えられたテーマは、うまくいかない」って、これは研究あるあるですよ。
首藤 最初にテーマを与えられたとしても、最後は自分の感性で見つけてきたものをやるところに、研究の面白さがありますね。
日野 でも、与えられたテーマを言われたとおりにやってた人は、ここにはいないと思うんですよ。
首藤 内的な動機があって、自分で研究を展開していく。やっぱり研究者になる人たちって、そういう人々じゃないでしょうか。
小野 研究者ってちょっと遠い存在だと思われがちですが、身近で、普通の人が研究しているんですよっていうのを若い世代に知ってもらえたら、研究の道に入りたい人が増えるかもしれませんね。
石黒 実際に研究者になって、皆さんイメージ通りでしたか?
小野 研究費を採るというプレッシャーはありますね。大学院の時に、試薬を1本買うのに研究費がなくて、「3カ月待ってくれ。そしたらお金が入ってくるから」って教授に言われたことがあります。その大変さは、当時理解できませんでした。
石黒 私は、生殖細胞で使う抗体が売られていなくて、自分で作って研究した時期がありましたよ。
首藤 「なければ作る」ですね。
日野 最近は、インフォマティクス(情報科学)思考の若い人が多いですね。泥臭い実験よりも、計算で多くの情報を導き出す人が、最近増えています。
首藤 研究者の定義自体が、昔と今で変わってきたと思いませんか?
日野 結果を出さなきゃいけないサイクルが早くなってるような気がします。これはいろんな方法論の合理化が進んでるってことですね。いい抗体ができたらそれだけでうれしいし、若い頃は日々の小さな“うれしい”の積み重ねで、メンタルを維持していました。
石黒 私は助教から一度、ポスドクに戻ったことがあるんですよ。就職活動がうまく行かなくて、いよいよ任期が残り半年ぐらいになり、ポスドクになると決めました。どこかの企業で会社のために研究する道もあるんでしょうけど、それは自分のために研究できる職業とはちょっと違う。今思えば、あの時ポスドクの道を選んでよかったと思います。
首藤 「自分のために」ってなんかいいですね。組織のためにとか、人々のためにみたいな話をよく聞きますが、やっぱり研究者の神髄に、自分の興味は重要ですから。
石黒 こういう職業ってあんまりないですよね。プロフェッショナルであり、自分の好きなことをやっていいっていう職業。多分、研究者以外には当てはまるものないんじゃないかな。ドイツの社会学者であるマックス・ウェーバーの著書「職業としての学問」に「学問を続けるのは『ぎょうこう僥倖』によって支えられて」という一文があるんです。「同僚や後輩が職を得て昇進している中で、自分はそうなれないとしても、『僥倖』とは運だと割り切り、学問に没頭できるのが学者としての資質だろう」と書いてありました。自分が助教からポスドクになった時に、心の支えにした思い出があります。
首藤 その状況で自分に資質があるって思い続けるってことはなかなか難しいですね。今、学生の皆さんに将来の話を聞くと「まだやりたいことがわかりません」という人が多い。そういう若者たちに対して、先生方からどんなことを言ってあげたいですか?
石黒 まずは飛び込んでみる、ですかね。
古賀 最初に楽しい実験に触れ合えば、きっと続けたくなる。最初に触れる時がすごく大切な気がします。
小野 私は、研究者という職業の選択肢を教えてもらったことが、きっかけの一つでした。もう一つは、運動生理学の実習で書いたレポートをすごく褒められたんですよ。そこで、何か勘違いした(笑)。
首藤 早めの成功体験で、いい意味での勘違いですね。言葉として面白い。ロールモデルに出会えたこともよかったですね。
石黒 発生研では、働きやすい環境整備や男女共同参画などにも取り組んでいますが、子育て中の古賀先生、率直な感想をお願いします。
古賀 発生研には、キッズルームや授乳室があり、いざという時には職場に子どもを連れてくることができる安心感があります。
石黒 発生研は、風邪をひいて、保育園に預けられない子どもたちを研究室のメンバーが世話をしたりしていますが、それができる研究所は他にはないでしょうね。
日野 先週、フランスから来客があって、発生研にはキッズルームや授乳室があると言ったら驚いていました。フランスでもそういうところはないそうです。
石黒 発生研では以前、女性教員の率が高かったんですよ。そこで授乳室を作ろうかっていう意見が出てきたんじゃないかと思います。
首藤 それはやっぱり「発生医学」というフィールドが女性研究者にとっては魅力的なフィールドだからではないでしょうか。
古賀 実験って自分でスケジュールを組めるので、子どもが熱を出しても、自分で実験を再調整できるので、研究職は女性にとっても働きやすい職業だと思います。授業参観なども、午前中に実験を仕掛けて行くことができますし。
石黒 そういった意味では、研究職というのは、本当に自由。子育て世代にとって、働きやすい職業だといえますね。
古賀 私は、保育園の延長保育は利用しないって決めて、その分、昼間にぎゅっと実験をつめていました。この日は遅くなるっていうときは夫と調整したり、土曜の朝も子どもがゆっくりしてる間に大学に行って用を済ませれば、一日中一緒に過ごせるし、工夫次第なんです。
日野 それは熊本のまちの規模感、職場と家と保育園・学校がかなり近い圏内におさまってるから。都心だとなかなかそういう生活は難しいでしょうね。
石黒 研究について考えてみると、使える実験機器とかがあれば、東京にいようが熊本にいようがあまり差はありません。しかし、他大学にはない熊本大学の大きな強みとして「動物資源開発研究施設」(以下、CARD)が挙げられますね。歴史的にも最初に遺伝子改変マウスを提供したのがCARDで、ここから理研をはじめ、日本全国に研究者やスキルが広がっていきました。皆さんはなぜ発生研を研究の場に選んだのですか?
小野 私にとって、発生研は憧れの研究所で、ここで働きたいという思いは、ずっと前からありました。入ったからには発生研を盛り上げて頑張りたいなって思います。
岡江 私は、研究を続けさせてもらえる場所があったらすごくラッキーだなっていう気持ちで就活していたんです。来てみて思ったのは共通機器の充実は本当にすごい! 一番驚いたのは、英語が半公用語みたいになっていることでした。
日野 私は「エピジェネティクスをやるなら発生研の中尾研究室」っていうほど、日本でも第一人者なので中尾先生の下で研究をしたくて門を叩きました。
石黒 オブザーバーとして参加いただいている熊大通信編集委員会委員の小出先生は、プラズマ物理学の研究をされていますね。
小出 現在プラズマの研究をしてるんですが、元々発生学には興味があります。例えば、DNAからタンパク質が合成される流れの概念「セントラルドグマ」は、現在も信じられているのですか。
石黒 現在では「セントラルドグマ」だけでは生命現象として説明がつかない、さまざまなメカニズムが明らかになってきています。例えば我々の分野でいう相転移は、熱力学の概念。相転移が生命現象でとても大事だと、7~8年ぐらい前からこぞってみんなが研究を始めて、流れが変わってきています。
首藤 発生や生物の学問分野は、研究者が追究していけばいくほど、科学の本質や生命の本質にたどり着く。それが発生学の面白さなのかもしれませんね。
小出 発生学ってそういう魅力のある学問だと思うんですよ。生命の本質を研究されてると思うとすごく興味があるんです。
石黒 生物学は覚える学問だといわれているんですが、実際にはロジックとか論理とかに基づく科学。「生物、全く知りません」っていう人でもそういうロジックをちゃんと理解して使いこなすようなセンスがあれば、専門的な知識はなくても、むしろ研究者向きだといえるでしょう。
小野 発生研は、生命の原理とか根幹を担うような研究が行われています。生殖とか、胎盤もそうですし、生命が生まれるところから研究している先生が多い。筋肉はただ動くだけじゃなくて、脳や肝臓、腎臓などの臓器にいろいろなシグナルを送っているんです。筋肉という生命の個体としての位置付けを捉え直すことなどが必要だと考えています。
小出 これまでは脳が全てをコントロールして、他の臓器はしもべのように動いているような印象でしたが、違うということですね。
小野 そうですね。腸からも脳に情報はいきますし、筋肉からも脳にも伝わっていることが分かってきました。臓器連関の視点が重要です。発生研の魅力の一つは、分野が異なる先生方からいろんな刺激を受けて、自分の研究にフィードバックできる環境だと思っています。
岡江 近年、「生命をつくる」研究が、本当に現実のものになりそうな段階になってきました。iPS細胞ができてから細胞レベルで実現可能になっています。だからもう精子もいらないし、卵子もいらないし、もうお母さんの子宮さえいらなくて。研究室の試験管の中だけで個体ができるっていうのは、実現可能な未来なんです。
首藤 まさに生命の本質みたいなものに関わるような研究ですね。それを自然にやってのけている人間の体ってすごい!
小野 発生研のメンバーがみんな集まって、それぞれの研究をつないでいくと、小さい人間、ミニヒューマンかなんかできるんじゃないかな?
石黒 そういう時代が来るかもしれませんね。
小出 試験管内で個体ができるようになれば発生過程の観察が進み、一つの受精卵から個体ができるまでの過程がたくさんの物理的な素過程から成り立っていることが明らかになるかもしれません。そうなれば発生の過程を計算機でシミュレーションすることができるはずで、実際に実験しなくてもよくなります。しかし、生命は単なる物理過程の連鎖でしかないのでしょうか。
石黒 興味深いですよね。もしかしたら、将来何年後かに発生研にもAIを活用してそのような研究を行う研究室ができるかもしれませんね。
日野 合成生物学では、分子から細胞を作ろうとしています。現時点では、細胞を細胞たらしめる最低限の要件は何かを定義していく段階です。まだ動物や植物の真核細胞ではできなくて、あくまでも微生物の原核細胞での話なんですが、遺伝子が400個あれば、細胞の状態になるといわれています。将来本当にそのような方法で個体ができるかもしれませんね。
石黒 いわゆる「役に立つ科学」(目的指向型で、比較的近いうちに社会実装が見込める研究)と「役に立たない科学」(現時点では、社会に応用できるかどうか分からない研究)についてどう考えていますか。それぞれ分けられるのかどうかとか、どちらに重点を置くべきだとか。私は、基本的に研究は自由であるべきだと考えているのですが。
小野 私が大学院で筋肉の研究を始めた当時、筋肉は重要な臓器とは認識されておらず、「なぜ心臓をやらないの?心臓も筋肉だし、そっちの方が大事でしょ?」という時代でした。自分の研究が応用につながればうれしいものですが、「知りたい! 面白い!」というのが研究のモチベーションですね。
岡江 私は役に立つ科学を目指すというよりも、自分の興味がある研究をしたいと思っています。研究費を集めたり、研究者として必要なことはやりますが、それはあくまで自分の好きな研究をするための一つの要素に過ぎないですね。
古賀 私は、臨床に貢献したいという思いがあるので、新薬を世に送り出すことが重要なモチベーションです。実際にやっていることが叶えたい夢に繋がっている、今の研究はすごく幸せだと感じています。
日野 個人的には基礎研究と応用研究の境目って考えたことはありません。応用要素のない基礎研究はないし、基礎要素のない応用研究はない。その先にある実用のラインに乗るかどうか、研究の次のフェーズが応用を左右するのではないかと思っています。農学部の出身として一つ気がかりなのは、応用の形として何か医療に役立たないといけないっていう縛りが強い気がするんですよ。でもそれ以外にも、例えば将来、確実に食料危機は訪れます。異分野の社会課題もある中で、基礎生物学がそういう食料生産に役立つことをまだ世の中に認めてもらっていないようで、それがとても残念ですね。
石黒 私たちは同じ研究所で研究をしていますが、こうして集まって語り合う機会はなかなかないので、一人ひとりの思いを聞いて、さまざまな気付きがありました。皆さん、ありがとうございました。

「肥後医育ミュージアム」で発生研の歴史などを体感した後に、分野を超えて語り合う研究者たち。石黒教授のコーディネートの下、それぞれの立場から多様な意見を交わす意義深い座談会となった。展示された史資料に感銘を受け、「今後は来客をご案内するなど、同ミュージアムを積極的に活用したい」という声も上がった

丹羽所長をはじめ、初めて訪れた研究者たちにとって、熊本大学の医学教育の原点を知る機会となった

発生研の系譜をまとめた資料に見入る石黒教授と古賀助教

古い顕微鏡や実験機器を見ることができる

前身である「体質医学研究所」の様子。この建物は、「医学部附属遺伝医学研究施設」時代にも使われており、当時大学院生として在籍していた丹羽所長が感慨深く見入っていた
発生研とは、いろんな視点を持った人が集まったプラットフォームであり、発生医学という分野のオールジャパンを集めたワンチームであることを皆さんが教えてくれました。そこで働く研究者の皆さんは、決して特殊な方々ではなく、誰もが持っている「自分なりの視点・感性・知的探究心」を具現化することで今を生きていると感じました。研究者って改めて魅力的な職業だなと、再認識しました。今後も発生研から世界へ発信を!