大名・細川家の魅力を海外にも届けたい!
―歴史を動かした細川家の知識と人脈の力―
熊本大学外国人客員研究員
アンドリュー・フィッシャーさん
インタビュー担当の健児くんです。
熊本大学にはさまざまなバックグランドを持った研究者や学生が日々研究に取り組んでいます。そんな中、今回は熊本県にもなじみの深い大名、細川家の研究に取り組む外国人研究員のアンドリュー・フィッシャーさんにお話を伺いました。フィッシャーさんはアメリカミシガン州出身で、セントルイス・ワシントン大学卒業後、イギリスのケンブリッジ大学院の博士課程に在籍しており、現在は博士論文の一環で、熊本大学永青文庫研究センターで研究をしています。
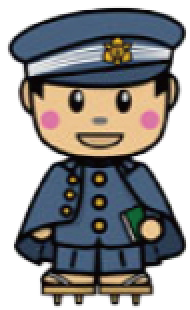
私はイギリスのケンブリッジ大学の博士課程で、肥後国(現在の熊本県)の大名であった細川氏について研究しています。もともと16世紀~17世紀のキリスト教宣教師と大名の関係性について興味があり、学部時代に研究を行っていましたが、研究を深める中で、武力ではなく、人脈や知識、情報力を駆使して名門大名の地位を築いた細川氏に強い関心を抱くようになりました。そこで、多くの細川家文書が集まっている永青文庫研究センターで現物の古文書を読み解きながら研究したいと思い、昨年10月から1年間留学しています。そして、研究センターでは細川家が天下統一を果たした主君にどのようにして仕え、名門大名家へと成長したのかを明らかにするための研究を進めています。
日本史に興味を持ったきっかけは、大学2年生のときに受講した日本史の授業です。それまで私は、日本についてアニメや文化をなんとなく知っている程度で、日本語もほとんど話せませんでした。アメリカの大学は日本と異なり、入学時に学部・学科が細かく分かれておらず、低学年のうちは幅広く教養科目を学びながら、徐々に専門を決めていきます。私もセントルイス・ワシントン大学に入学した当初は、特に明確な目標があったわけではなく、母親が同じ大学の医学部出身だったこともあり、自分もその道を進むのだろうと漠然と思っていました。
しかし、大学2年生のときに教養科目として日本史を受講した時に、その面白さに魅了されたんです。授業を受ければ受けるほど、この研究をもっと深く学びたいという思いが強くなりました。そこで、担当の先生に相談したところ、「日本史を研究するなら、まず日本に長期間滞在し、日本語を習得したほうがよい」とアドバイスを受け、大学3年生のときに大阪府枚方市へ1年間ホームステイしながら、京都で日本語や日本社会を学びました。
 |
そうですね、私は日本留学するまでは戦国時代の権力争いに興味を持っていましたが、留学をする中でキリスト教の宣教活動に興味が変わりました。例えば、戦国武将の織田信長の時代は、フランシスコ・ザビエルを初めとするキリスト教宣教師の活動が広く認められ、次第に大名の中にもキリスト教に改宗したキリシタン大名が現れました。
ただ、私はキリシタン大名が必ずしも心からキリスト教を信仰していた訳ではないと思うのです。中にはただ外国への憧れが強かっただけの大名もいるでしょうし、鉄砲などの武器を手に入れやすくするために信仰していた大名もいると思うのです。そのように、キリスト教を中心とした日本の政治社会と人間関係に興味をいだき、卒業論文で研究しました。
はい、2019年に大学卒業後、2年間は愛媛県の伊方町でALTとして子どもたちに学校で英語を教えていました。私も日本語を学んだことを機に言語に興味が湧いていたのもありますが、子どもたちに言語習得の楽しさや自分の経験を共有したいと思ったんです。文法や読み・書きばかりにとらわれず、どうすれば英語でコミュニケーションがとれるのか、それを教えることを頑張りました。
母語と同じように学ぶことが重要だと考えています。幼い子どもは親の言葉を聞いてまねることを最初にすると思います。私もそれと同じように、最初はホストファミリーが話す日本語を聞いて、まねて、そして筋トレのように毎日継続して取り組みました。そして徐々に日本語での議論ができるようになってから、読み・書きの練習を始め、日本語を習得することができました。
 |
いつか大学院に進学し、博士号を取得したいとはずっと考えていたことです。ですが本格的に考え始めたのは、ALTとして働いていた2年目の2020年です。この時期は新型コロナウイルスの流行が始まり、外出も制限される中で、自分の将来についてじっくり考える時間が多くありました。その中で「やはり日本史を研究したい」という思いがより一層強まったんです。
しかし、当時の私は大学院ですぐに研究を進めることができる程の十分な知識を持っていませんでした。日本史、とりわけ前近代史を研究するには、古文や漢文を理解する力が不可欠です。そこで、ALTとして働きながら少しずつ準備を始め、ALTを終了した後は、日本研究を志す人向けのアメリカ・カナダ大学連合日本研究センターに入学しました。1年間、古文や漢文を学ぶとともに、日本の前近代史に関する基礎知識を深め、並行していくつかの大学院に出願しました。
ケンブリッジ大学の日本研究が非常に優れていたことが主な理由です。さらに、私の指導教官は前近代日本史の研究者として高く評価されており、その先生のもとで学べることは大きな魅力でした。
それに加えて、私は以前からヨーロッパに対する憧れを持っていました。アメリカも素晴らしい国ですが、もっと長い歴史を持つ国で育ってみたかったなという思いをずっと持っていたんです。そのため、歴史の深いイギリスで研究や生活してみることに惹かれ、ケンブリッジ大学に進学しました。
博士論文では、当初の研究内容から少し変化がありました。研究当初は、日本におけるキリシタン時代の研究をしていましたが、研究を進める中で細川ガラシャという魅力的な人物に出会い、彼女をきっかけに細川家の歴史に強く興味を持つようになりました。
しかし、欧米における日本史研究では、島津家などの他の大名について書かれた英語の論文は多くあるものの、細川家に関する英語の論文はほとんどありません。だからこそ、博士論文では未開拓の分野である細川家を研究したいと思い、現在は主君との間で、細川家がどのように人間関係を築いたのかを研究しています。
一言で表すならば、“生き方”ですね。細川ガラシャは明智光秀の娘で、幼い頃から聡明だったといわれています。細川忠興に嫁ぎますが、本能寺の変で父・明智光秀が織田信長を討つと、ガラシャも京都の屋敷に幽閉されるなど、政治に巻き込まれた大変な人生を送ることになります。そのような大変な幽閉生活の中で、ガラシャは次第にキリスト教に興味を持つようになり、カトリック教徒になりました。
ただ、この時代は豊臣秀吉下でキリスト教の宣教師が国外追放されている時代。夫・忠興からも信仰を反対されるなど、ガラシャは新たな逆境に直面します。それでも、ガラシャは最後まで信念を貫き、関ヶ原の戦いが起こると敵の人質となることを拒み、最後まで信仰を守り抜きました。
私はもしガラシャが現代に生きていたら、きっと学者になっていたのではないかと思っているんです。彼女は外国の文化や哲学、宗教、芸術など幅広い分野に関心を持ちながら、逆境にあっても諦めずに信念を貫きました。そのような強い生き方に魅力を感じました。
細川家は、単に武力によって名門大名となったわけではありません。人とのつながりや文化の力、そして情報を集める力をうまく使ったことで、大名としての地位を固めていきました。たとえば、茶の湯や和歌といった文化を大切にすることで、武将や貴族たちとの関係を深め、時代の流れをよく読み取り、正しい判断をすることで、生き残ることができたのだと考えます。
また、特に興味深いのは細川家が「忠誠(忠義)」を非常に重視していた点です。彼らの文書には「忠義」という言葉が頻繁に登場し、主君との関係を維持する上で重要な役割を果たしていました。これは、現代の政治にも通じる考え方であり、たとえばアメリカのトランプ大統領も「忠誠」の重要性を度々強調していると思います。歴史を振り返ると、リーダーにとって忠誠心は極めて重要な要素であり、細川家もその重要性を深く理解していたと言えるでしょう。
このように、細川家の成功は、現代の社会にも通じるヒントを与えてくれます。お金や力がなくても、知識や人とのつながりを活かせば、大きな成功をつかむことができる。細川家の歴史を知ることで、人との関係の大切さや、リーダーシップの本質を学ぶことができるのも、とても興味深いところです。
私は主に16世紀の資料しか扱っていませんが、細川家は江戸時代以降も生き抜いた大名家であり、そのため現代でも数多くの資料が残されています。これだけ多くの貴重な資料が現存していること自体、非常に素晴らしいことだと思います。また、先ほどもお話ししましたが、細川家は武力以外にも非常に高い能力を持ち、重要な選択を鋭く判断してきました。大名家の中でも、特に賢明な判断力を持つ家系だと感じています。こうした資料の価値が認められ、国の重要文化財に指定されることは、細川家の歴史的な重要性を再確認する意味でも大変意義深いことです。
熊本大学での研究をもとに博士論文を執筆しており、現在ほぼ完成しています。留学が終わる9月までに仕上げ、帰国後に提出する予定です。順調にいけば、来年3月に卒業できる見込みです。
卒業後は、この博士論文を本として出版したいと考えています。特に、永青文庫研究センターでの細川家に関する研究を、より多くの外国の方々にも知ってもらえるような形にしたいですね。ただ、博士論文は専門的な内容が多いので、今後は一般の方にも理解しやすいように工夫して制作に取り組みたいと考えています。
 |