動物モデルで免疫反応を解析
―ウイルス研究に挑む大学院生の挑戦―
医学教育部博士課程 3年次
黒川さん
インタビュー担当の健児くんです。
熊本大学には教員以外にも日々様々な研究に取り組んでいる学生がいます。そんな中、今回はウイルスと免疫の関係解明に取り組む博士課程の学生にお話を伺いました。研究の最先端で活躍する大学院生が考える研究の魅力とは...ぜひご覧ください!
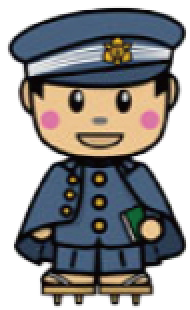
私たちの研究室では、それぞれの大学院生が複数の研究テーマを持っているのですが、私はヒトレトロウイルスの代表例であるHIV(ヒト免疫不全ウイルス)をテーマの一つとしています。HIVは免疫細胞に感染し、治療を行わないと最終的には免疫不全を引き起こしてしまうウイルスです。HIVに感染した細胞の一部は「リザーバー」と呼ばれ、薬や免疫の影響を受けにくい組織に残存します。そのため、ウイルスの排除が難しく、継続的に薬を飲み続けなければならない現状があります。そこで、組織ごとのリザーバーの特徴やリザーバーに対し有効な免疫反応を明らかにするために、それを模した動物モデルをつくろうというのが今取り組んでいるテーマの一つです。
トランスジェニックマウスという動物モデルを用いています。これは人工的に遺伝子を改変したマウスのことを指します。そもそもHIVとはすべての動物が感染するものではなく、マウスは感染しません。そのため、マウスの遺伝子の中にHIVのタンパク質の一部を組み込み発現させることでHIVに感染したマウスを模倣しているんです。
ただトランスジェニックマウスを作るには数世代にわたりマウスを交配させねばならず非常に時間がかかるものです。私はこの研究室に来て3年目になりますが、最近になってようやく新規トランスジェニックマウス系を樹立することが出来ました。現在は、動物モデルとしての運用を目的とした実験スケジュールの策定や適した行動解析の検討を行っているところです。
もう一つの研究テーマは新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の重症化メカニズムに関連する研究です。コロナ禍においてはよく「高齢者の方が重症化しやすい」といわれていたかと思いますが、私たちは特に年齢による病態決定のメカニズムを明らかにすることを目的としています。マウスもヒトと同様に、高齢になるとSARS-CoV-2による肺炎が重症化しやすい傾向があることから、私たちの研究室ではマウスモデルを用いることで重症化を引き起こす免疫学的な要因を解析しています。
研究について興味を持ち始めたのは高校生の頃です。私が通っていた高校は理系教育に重きが置かれており、その一環で大学の先生に研究内容を紹介してもらう授業がありました。そのときに紹介してもらったテーマが「ニワトリ胚の発生から人体の形成過程を探る」というもので、講義後、学生たちで自発的にテーマを決めて研究計画書の作成や夏休みを利用した研究活動を行いました。シャーレでニワトリ胚を培養するための環境を作って、どうやったらシャーレ上でも長く生きられるのか考えて・・・などトライアンドエラーを繰り返した経験がとても楽しくて、その時なんとなくですが研究っていいなと思いました。
その後、大学では臨床検査の道に進み、学部4年時には患者さんの細胞からどのような病変があるのかを読み解く細胞診を学びましたが、やっぱり研究は面白いと思い、修士課程では感染症の研究を始めました。
きっかけは国立感染症研究所が開催した若手や学生向けの説明会に参加し、HIVを研究している先生と出会ったことです。それまでもウイルスに興味はあったのですが、具体的にどんな研究がしたいかまではイメージできていませんでした。そんな時、先輩からの誘いで参加した若手/学生向け説明会で実際に研究の第一線に立つ先生方と出会いました。その先生方のお話は非常に魅力的で面白く、自分もそのような先生の下でHIVの研究をしたいと強く思いました。
学部時代に所属していた臨床検査技術学科の学生は病院に就職することが多いんです。ですので、私もそのような道もあったんですが、研究が好きだという気持ちと、HIV研究の魅力に惹かれ、臨床から基礎研究という異分野ではありましたが、修士課程ではその先生が所属している熊本大学に進学しHIVの研究を始めました。
進学したのはやはり研究が楽しいと感じたからです。修士課程に入学したときは2年もあれば研究とはどんなものか分かるはずと思っていましたが、いざ研究に触れてみると2年では1つの仕事をまとめるのにすら十分な時間ではないと実感しました。自分が関わったプロジェクトを計画の立案から論文としてまとめるまで、すべての経過を経験してみたいと思ったので博士課程に進学しました。
 実験服 |
研究時間はフレックスなため、学生やその日の仕事内容によっても変わるのですが、私は10時頃に研究室に来て20時頃帰ることが多いです。ずっと研究室でパソコンに向かっている日もあれば、1日中実験室にこもって実験している日もあります。私はアルバイトやサークル活動をしていませんので、基本的に研究を終えた後は家に帰り、次の日のためにリラックスしています。
研究生活の中で一つ大変なことがあるとすれば、動物を扱う実験をしていますので、「毎日11時にマウスの体重を測定する」と決めたら休日に関わらずスケジュール通りに進めなければならないことです。ですから、必要に応じてマウスの体調管理のために土日も1~2時間程度実験室に来ることもあります。ただ、私たちの研究室はチームで研究をしていますので、ペアをつくって交代で取り組んだりと、一人が負担になりすぎないようにはしています。
私は東京都出身で、熊本のことが詳しくないため、研究以外の時間は熊本観光をすることが多いです。特に温泉を巡ることが好きなので、近場のサウナ付きの温泉に行ってリラックスしたり、たまには車を出して日帰りで温泉旅行に出かけたりすることもあります。
この研究室ではフレックスに研究に取り組んでいるため、自分の立てたスケジュールが順調に進んだときや、些細なことでも自分で課題を見つけてそれを解決するためにトライアンドエラーを繰り返す中でうまくいったときは、とてもうれしいです。もちろんうまくいかないことも多いのですが、とりあえず試してみることが大切だと思っています。
それぞれ得意・不得意があるかと思いますが、お互いそこを補い合える雰囲気があります。たとえば、研究の進捗状況をみながら困っていそうなことがあれば「大丈夫?」と声をかけあうこともありますし、研究の悩みを相談し合うこともあります。
 研究室での誕生会の様子 |
学部時代に学んだ臨床検査技師としての基礎知識や、細胞診を学んだ経験は博士課程の現在でもとても役に立っています。例えば、病理の標本を見たときに「この組織は炎症を起こしているな」とか「病変がみられる細胞はこの種類の細胞だな」など様々な所見が得られることは、細胞診の経験がなければ難しかったと思います。また、実験を行う際のピペットの使い方や病原性のある検体の扱い方に関する基礎知識は今も欠かせないものとして生かされています。
学部生時代にもっと取り組んでいたら良かったことは、英語です。私たちの研究室は留学生の割合が高いので、日常的に英語で会話をしています。また熊大の博士課程では基本的に国際誌に論文を一本は出す方針がありますので、英語ができるに越したことはないと思います。ただ「住めば都」という言葉があるとおり、最近はこの環境にも慣れ、英語でのコミュニケーションに苦労することも少なくなってきましたので、そう心配しすぎる必要はないと思います。
私たちの研究分野であれば、大きく分けて二つの進路があると考えています。一つは大学に残って研究を続ける道、そしてもう一つが企業や研究所の研究員として研究に取り組む道です。この二つの大きな違いは裁量性を持って研究に取り組むか、あらかじめ課題が提示されていてその解決に取り組むかだと思います。私はどちらにも良さがあると思いますので、まだはっきりと進路を決めていませんが、今後じっくりと考えていきたいと思っています。
 タンザニアの大学でセミナー発表を行った際の写真 |