子どもの視線から発達障害を解明する
「見える化」することで早期支援につなげる
大学院生命科学研究部 環境社会医学部門 看護学分野 地域・公衆衛生看護学講座
大河内 彩子 教授
- 所属
VR(仮想現実)ゴーグルを使って視線を計測し、発達障害の子どもの特徴を明らかにする研究に取り組んでいるのが、大河内彩子教授です。視覚や聴覚、触覚などの感覚の研究は、最近注目されるようになりました。データにして「見える化」することで発達障害に対する理解を促し、早期の支援につなげることが目的です。
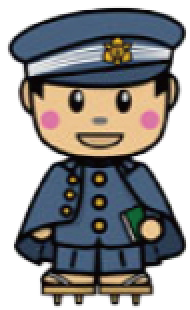
視線から子どもの発達障害を解明する研究をしています。発達障害の子どもと定型発達の子どもの視線を比較し、データにしてできるだけ「見える化」することで、発達障害の子どもの視線の特徴を出したいと考えています。
この研究は、看護学と工学の「看工連携」で進めており、先端科学研究部(工学系)の松永信智教授のご協力のもと、VRゴーグルに仮想の教室での授業風景を映し、0.05秒ごとに子どもがどこを見ているのかを計測するシステムを開発しました。松永研究室の大学院生たちも、子どもの親御さんにどうしたら分かりやすく結果を説明できるかを考え、試行錯誤してくれました。
当初は発達障害の子どもは視線が動き、キョロキョロするのではないかと考えていました。ところがデータを見てみると、集中して先生をじーっと見ている傾向がありました。先生のイラストを使用したため、イラストが好きだったという可能性はありますが、発達障害の子どもは「集中力がない」のではなく、「集中しすぎる」ために疲れてしまって、結果的に「集中力がない」と周囲に思われてしまうのだと思います。
教室には水槽を置いたほか、ノートが机から落ちる音や猫の鳴き声、「焼き芋~」という声など音の刺激も発生させていたのですが、発達障害の子どもはほとんど注意を向けませんでした。ところが、先生がどんな話をしたかというクイズを出すと、正答率が低かったんです。つまり、先生を見ているのに、話は頭に入っていない。好きなものには集中できる一方、集中力をバランスよく分散させることができないのです。一方、定型発達の子どもは、先生を見たり黒板を見たり、集中力を適度に分散させていました。
 (VRゴーグルで写しだした仮想の教室の映像) |
 |
「こういうことなんですね」と言って、受け入れてくださいます。親御さんが学校の先生に配慮を頼んでも、先生からするとその子どもは「授業中、前を見ているので問題ない」と思われていることがあります。しかし、前を見ていても話は頭に入っていないので、「学校の先生にこのデータを見せれば、配慮をお願いしやすくなる」と言われた方もいました。
1時間話を聞いていても、得る量がほかの子と比べて2割程度しかないとしたら、あとの8割をどこかで補わないといけません。そのままにすると学業が遅れてしまい、学校に行くのがつらくなっていく可能性があります。学校の配慮を受け、早期に支援につなげられるようにしたいと思っています。
発達障害の子どもの視線に関する研究はほかの大学でもされていますが、これだけ詳しいデータを取っているのはほかにないと思います。看工連携のおかげです。
発達障害に関しては社会性の障害、コミュニケーションの障害と言われていましたが、最近、視覚、聴覚、嗅覚、味覚、触覚という感覚が特殊なのではと言われるようになりました。発達障害のある子どもは感覚調整障害もあるケースがあります。発達障害は気づかれにくく、当事者や親も困りごとがあっても、理由が何なのかよく分からないことがあります。感覚を「見える化」することで、困難を「見える化」したい。自分の状態を知ることで理解できるようになり、人に対して助けを求めやすくなります。
 |
感覚が過敏で、触られるのを嫌がる子どももいます。抱っこを嫌がってのけぞるので、抱きにくい。抱っこするより、板の上に寝かせると落ち着く子どももいます。しかし周囲から、「あのお母さんは子どもを板の上に寝かせるなんて、冷たい」と言われてつらかったという母親もいました。感覚が過敏なために寝かせつけるのもひと苦労です。大変苦労して育てているのに、周囲から理解されにくいという面があります。
また、施設の方にご協力をいただいて、虐待を受けた発達障害の子どものデータを取らせてもらいました。虐待を受けていない発達障害の子どもは触覚が過敏な傾向がありますが、虐待を受けた子どもは鈍いという結果が出ました。虐待を受けると、感覚を麻痺(まひ)せざるを得ないのだろうと思います。感覚に過敏な子ども、逆に鈍い子どももいますので、感覚に対する配慮が求められています。
私自身、過労で突発性難聴になったことがあります。難聴になった直後は音に対して過敏になりました。音に攻撃されているような感覚になったのです。「外は音がうるさいので、外出ができない」という人がいますが、「こういうことなんだ」と実感しました。とてもしんどいのに、あまり知られていません。運動会でスタートの合図のピストルの音も、聴覚が過敏な人にとっては我慢ができず、パニックを起こしてしまうことがあります。感覚に関する研究が必要だと思いました。
感覚が過敏になることもあれば、逆に鈍麻になることもあります。例えば「おなかが空いた」という感覚が分かりにくく、食べないでも平気な人もいます。それでは命に関わってしまいます。感覚に対する研究は遅れています。感覚に関する困りごとを「見える化」することで、発達障害の人の困りごとを知ってもらい、本人たちが生きやすくなればと思っています。
視覚の研究から、個別の支援の方法を考える研究をしたいと思っています。熊本大学には教育学部附属特別支援学校があるので、教育学部の先生と一緒に研究できたらと考えています。
生身の人と対面すると緊張してうまく話せない発達障害の人が、VRゴーグルなど新しい技術で異空間に行くと、自由に話せるようになるケースもあります。自分で作った分身(アバター)で本音を話せるかもしれない。今の若い人たちはデジタル技術に親しんでいるので、こうした技術を利用することで、当事者の心の声を聴きたいと思っています。
世の中で大きなことを成し遂げた人の中には、発達障害の人もたくさんいます。いい面もたくさんあります。聴覚が過敏で、機械の調子が悪くなる前に機械の異音を聞き分けられる能力があるとして、雇用につながった人もいます。いい面を生かし、発達障害があっても幸せになれる社会につなげていけたらと思っています。
 |